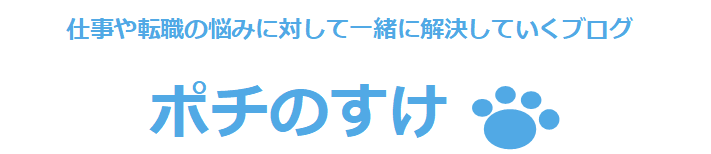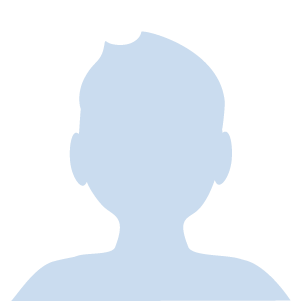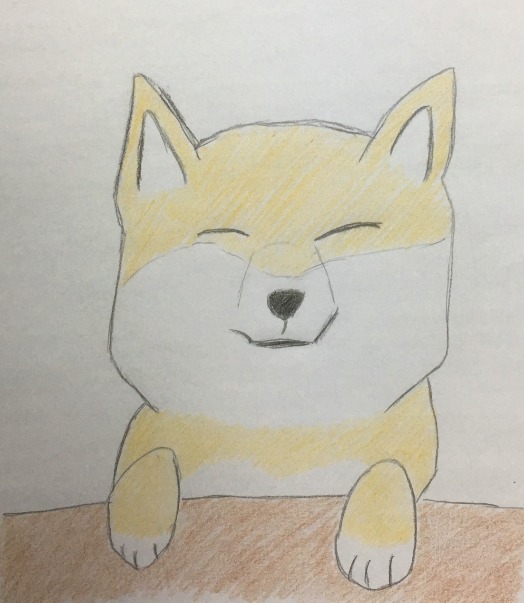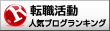~本ページはプロモーションが含まれています~
というお悩みにお答えします。
3回転職した中で、退職するまでの間に気まずい思いをしたことがあるポチのすけ(@pochinosuke1)です。
自身の経験から、退職までの期間を乗り越えるための心構えとやるべきことが分かるようになりました。
転職活動で内定が出た後の退職するまでの間は、心機一転してわくわくしながら過ごせることもありますが、職場によってはつらい思いをすることもあります。
例えば、
- 自分も辞めたいと思っている同僚からの妬み
- 辞めることに対して嫌がらせをしようとしてくる上司
など、残念ながらあなたの門出を祝福してくれない人もいるのが現実。
せっかく次の職場が決まったのに、退職までの期間が気まずいと、毎日が憂鬱でストレスを抱えてしまいますよね。
本記事では、転職などで退職が決まったものの、
「退職までの期間が辛くて気まずい。。」
とお悩みの方に、ぼくの経験から
- 退職までの期間を乗り越えるための心構え
- やっておくべきこと
についてご紹介していきます。
結論から言うと、心構えは以下の2つ。
- 割り切る
- 次の職場への準備期間と考える
やっておくべきことは、以下の2つになります。
- 書類関連
- 引継ぎ関連
本記事後半では、
- 退職までの期間が辛くて限界の方が取るべき方法
についても解説しているので、是非最後までご覧ください。
退職までの期間が耐えられない人におすすめの退職代行サービスはこちら!
- 利用者数NO.1で価格もリーズナブルな退職代行SARABA
- 弁護士による安心の退職代行サービス弁護士法人みやび
退職までの期間が辛くて気まずい時に乗り切るための2つの心構え

退職が決まった後、
- 上司や同僚があからさまに無視してくる
- 陰口をわざと聞こえる声で言ってくる
という状況だと、つらいです。
退職までの気まずい期間を乗り切るための心構えは、以下の2つ。
- 割り切る
- 次の職場への準備期間と考える
心構え①割り切る

退職までの期間が辛くて気まずい時、退職までの期間を乗り越えるために持っておくべき心構え1つ目は、割り切ること。
特に、まじめな人ほど苦しみやすいので、辞める職場の人とはもう二度と会うことはないと考えれば楽になります。
できれば快く送り出してもらいたいのですが、世の中にはいろんな人がいるので、
- 急によそよそしくなる
- 質問しても返事を返してくれない
という形で、冷たく当たってくる人もいます。
ブラックな職場だと、同僚も辞めたいと思っているので、
「俺も辞めたいのに、なんであいつだけ。。」
という理不尽な妬みから、今まで通り接してくれないこともあります。
上司も、部下が辞めることで自分の評価が下がることを気にして、ストレスのはけ口にしようとしてくる場合も。
そんな時は、無理に頑張らなくてOK。
「もうこの会社は辞めるから、この人たちとは二度と会うことはない。」と割り切ることで、何か言われてもただの雑音だと聞き流すことができるようになります。
また、退職するまでの間に
- しつこく引き止めされる
- 妨害を受ける
ような場合でも同様に、割り切ることで乗り越えることが可能。
昔話題となった
- 部屋に監禁する
- 懲戒解雇する
といったものではありませんが、あなたの良心につけ込むような意地悪な言い方をして、
- 退職時に引き止める
- 妨害してくる
場合でも、割り切ることで乗り越えられます。
詳しい内容は、下記の記事で解説しています。
退職引き止めがしつこい時に乗り切る心構えについての詳細記事はこちら

心構え②次の職場への準備期間と考える
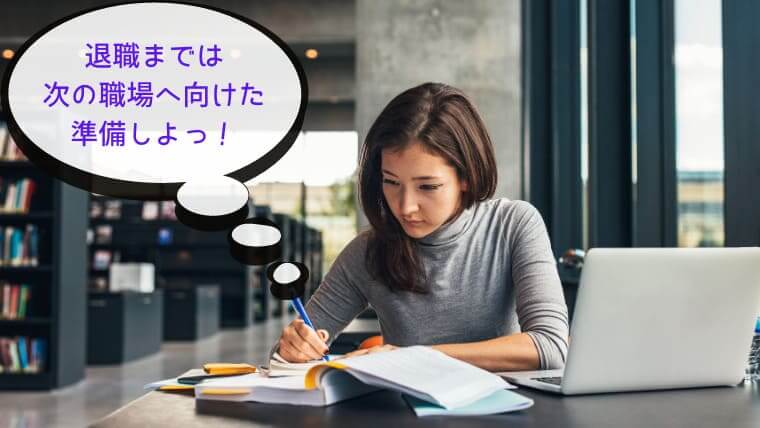
退職までの期間が辛くて気まずい時、退職までの期間を乗り越えるために持っておくべき心構え2つ目は、次の職場への準備期間と考えること。
「あと10日我慢すれば、解放される。」というような考え方だけでなく、発想を変えることで楽になります。
退職が決まっているのなら、残り期間を次の職場に向かう時までの準備期間(ウォーミングアップ期間)と考えると、前向きな気持ちになるので楽になります。
今の職場の良いところ・悪いところを観察することで、次の職場で活かせる良い準備期間に。
あくまで、今の職場で頑張るのではなく、今後の自分のために準備するという考え方です。
なお、次の職場に向かうまでの期間をスキルアップ期間として過ごすことで、退職するまでの辛いだけの期間がレベルアップ期間に変身!
退職までの期間にもレベルアップしておくと、次の職場で早く活躍しやすいのと、できることが増えて年収アップにつながりやすいです。
退職するまでの期間に自分自身をレベルアップする方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職までの間に自分自身のレベルアップをする方法の詳細記事はこちら

退職までの期間にやっておくべきこと

退職までの期間が辛くて気まずい場合でも、やっておくべきことがあります。
退職までの期間にやっておくべきことは、以下の2つ。
- 書類関連
- 引継ぎ関連
これらを淡々と行っていきましょう。
また、職場が変わることで引っ越しをする必要がある場合は、合わせて行うことも忘れずに。
やっておくべきこと①書類関連
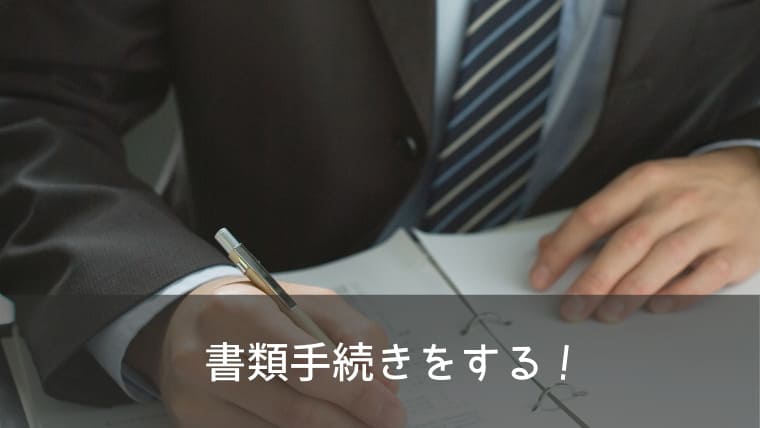
退職までの期間にやっておくべきこと1つ目は、書類関連。
書類関連でやることは、以下の3つです。
- 現職での書類の手続き
- 転職先への書類の手続き
- 確定拠出年金やiDeCo(イデコ)をやっていれば手続き
会社側から連絡してくれるものが多いですが、将来のために確定拠出年金やiDeCo(イデコ)をやっている方は忘れずに行っておきましょう。
①現職での書類の手続き

現職での書類の手続きは、人事の方から色々と必要書類をもらうので、確認しながら進めましょう。
人事の方から住民税の支払いについて、
- 最終給与から天引きする
- 自分で支払う形にする
のどちらがよいか聞かれますが、どちらにしても払うので最終給与から天引きしてもらいましょう。
会社携帯など、会社からの支給品を無くしてしまうと最終給与から天引きされてしまうので注意しましょう。
特に、会社携帯の充電器やイヤホンなどは私物とごっちゃになりやすいので、日頃から気をつけておきたいもの。
②転職先への書類の手続き
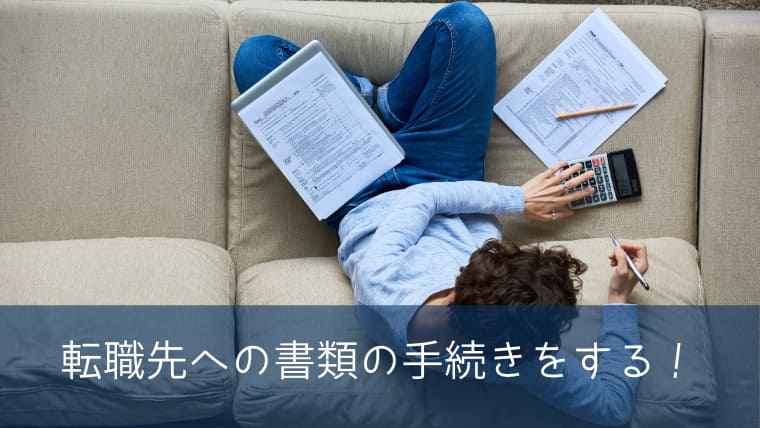
結構面倒なのが、転職先への書類の手続き。
新しい職場の人事の方から必要書類が届いたら、
- 入社前にやる書類
- 入社後にやる書類
があるので、まずは入社前にやる書類を進めましょう。
入社前の書類は、
- 年金番号の記載
- 誓約書への親族の捺印
など細かいものが多くて面倒ですが、必要なものになるので、全体像を押さえてさっさと済ませてしまうのがおすすめ。
退職証明書などの書類は、入社後に提出する形になります。
また、書類ではありませんが、会社によっては入社前に健康診断を受ける必要があるところもあります。
ぼくも3社目に入る際、入社前に健康診断を受ける必要があると指示があったので、病院に行きました。
③確定拠出年金やiDeCo(イデコ)をやっていれば手続き
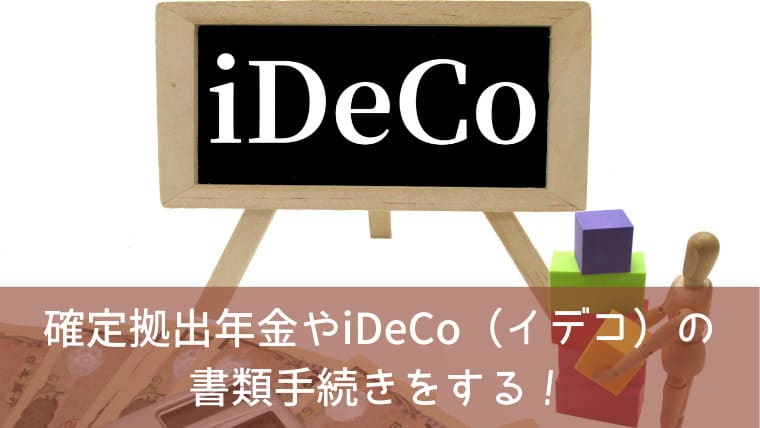
書類関係で自分で手続きしないといけないのが、確定拠出年金やiDeCo(イデコ)といった個人年金。
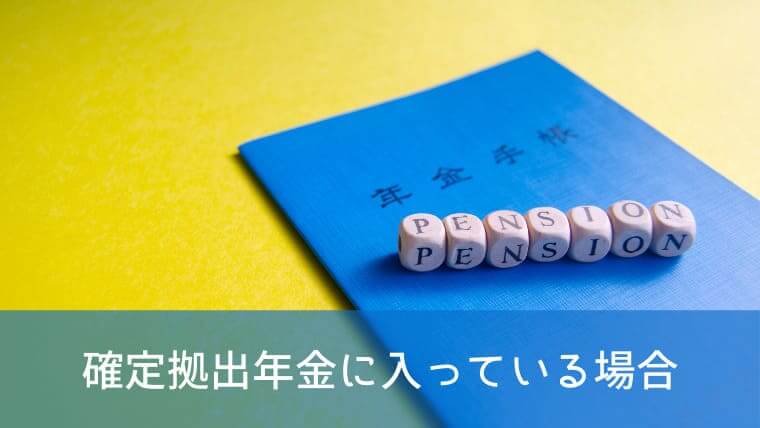
確定拠出年金は会社によって対応しているところと、対応していないところがあります。
現職の会社では対応していても、転職先で対応しているかどうかは必ず確認しましょう。
転職先で確定拠出年金に対応している場合
全員加入なのか、任意加入なのか確認しましょう。
全員加入の場合は、確定拠出年金のお金を転職先の会社の確定拠出年金に移します(移管)。
任意加入の場合は、転職先の会社の確定拠出年金に移すか、個人型確定拠出年金であるiDeCo(イデコ)に入るようにしましょう。
転職先で確定拠出年金に対応していない場合
iDeCo(イデコ)に入るようにしましょう。
参考までにお伝えすると、転職する方だけでなく、フリーランスとして独立する方や、専業主婦として退職する方も同様になります。
手続きは以下の通り。
- iDeCo(イデコ)の書類をもらう
- 必要な書類を返送
- iDeCo(イデコ)への移管が完了
移管完了までは1~2ヶ月かかることが多いです。
加入者資格を喪失(退職)してから6ヶ月以内に移管手続きをしないと、前職での企業型の資産はすべて現金化され、「国民年金基金連合会」へ強制的に移換されてしまいます。
強制的に移管されると、
- 余計な費用がかかる
- 運用ができない
などのデメリットしかないので、忘れずに転職時には手続きをしましょう。
iDeCo(イデコ)はたくさんの証券会社や銀行がやっていますが、おすすめは楽天証券やSBI証券などのネット証券。
余計な手数料がかからず最安値でできるのと、通常の資産運用よりも数が少ないiDeCo(イデコ)の中でも、良い商品を取り扱っているからです。
楽天証券やSBI証券がおすすめの理由については、下記の記事で詳しく解説しています。

転職先の会社でもiDeCo(イデコ)ができるのか、確認しておきましょう。
会社によっては、確定拠出年金の全員加入が必須でiDeCo(イデコ)ができない場合があるからです。
なので、転職先の会社が確定拠出年金への加入必須なのかどうか、必ず確認しましょう。
転職先の会社が、確定拠出年金への加入必須の場合、転職先の会社の人事の方に確認すれば、手続きを教えてくれます。
転職先で確定拠出年金への加入が必須の場合
iDeCo(イデコ)のお金を転職先の会社の確定拠出年金に移します(移管)。
書類上の手続きが必要。
詳細は、転職先の会社の人事の方に確認して進めましょう。
転職先で確定拠出年金がない、または確定拠出年金があるけどiDeCo(イデコ)の同時加入が可能な場合
そのまま、iDeCo(イデコ)を継続することができます。
参考までにお伝えすると、転職する方だけでなく、フリーランスとして独立する方や専業主婦として退職する方も同様になります。
ただし、iDeCo(イデコ)を継続する場合でも、転職すると会社が変わることから手続きが必要になります。
手続きの段取りは、以下の通り。
- iDeCo(イデコ)をやっている証券会社から書類をもらう
- 必要な書類を書いて転職先の人事の方に渡す
- iDeCo(イデコ)への移管が完了
移管完了までは1~2ヶ月かかることが多いです。
ぼくは楽天証券でiDeCo(イデコ)をやりながら転職しており、その時にどのような手続きをしたのかを下記の記事でまとめています。
どの証券会社でも似たような形になるので、参考にしてみて下さい。
さらにぼくの場合は、転職先では企業年金基金に入っていなかったこともあり、月12,000円しか積み立てられなかったのが月23,000円まで積み立てられることになりました。
ただ、転職先の会社が企業年金基金に入っていると、iDeCo(イデコ)ができても金額が限られるので対策が必要。
ぼくは日本ITソフトウェア企業年金基金という企業年金基金に入っている会社にいたことがあるので、下記記事でどう対策するべきか詳しく解説しています。
iDeCo(イデコ)はたくさんの証券会社や銀行がやっていますが、証券会社によって投資できる商品がかなり違ってきます。
転職をきっかけに良い証券会社に変えるのもおすすめ。
ぼくがおすすめするのは楽天証券やSBI証券などのネット証券。
余計な手数料がかからず最安値でできるのと、通常の資産運用よりも数が少ないiDeCo(イデコ)の中でも、良い商品を取り扱っているからです。
楽天証券やSBI証券がおすすめの理由については、下記の記事で詳しく解説しています。
やっておくべきこと②引継ぎ関連

退職までの期間にやっておくべきこと2つ目は、引継ぎ関連。
引継ぎは、自分の担当している仕事をスムーズに引継ぎできるようにしましょう。
まずは誰にどう引き継ぐのかを上司と相談。
引き継ぐ人が決まったら、以下の情報を正確に伝えましょう。
- 経緯
- 現状
- 今後について
また、ぼくのような営業職の場合は顧客への挨拶は必須。
メールや電話のみで済ませるのか、引き継ぐ人と一緒に訪問するべきなのかは顧客との関係性によって変わってきます。
どちらにしても、まずはメールで挨拶するのが必要。
退職時の挨拶メールで、
- 書くべき内容
- メールを送るタイミング
など、ぼくが実際に送っていた文章も書いているので、下記の記事を参考に書いてみて下さい。

また、引継ぎを済ませたら、職場への挨拶とお菓子を置いておくのも忘れずに。
近くにお菓子を買うところがなかったら、Amazonや楽天市場で探しましょう。
SEの方で、客先常駐・SESの契約期間中に退職する場合、きちんと引継ぎを行いましょう。
最終出社日の1ヶ月ぐらい前に所属会社の上司に退職の旨を伝えておき、その間に引継ぎを行えばOK。
客先常駐・SESを辞める時の段取りは、以下の通り。
- 契約期間とプロジェクトの内容を確認する
- 転職エージェントに相談して求人確認する
- 転職候補企業の口コミをチェックする
- 面接対策をして転職活動を行う
- 転職先が決まったら所属先の上司に退職を伝える
- 最終出社日前に引継ぎを行う
- 最終出社日は所属会社に退職のメールを送る
- 最終出社日の後は有給休暇をフル消化する
きちんと段取り組んで動かないと、退職時にトラブルになるので気をつけましょう。

なお、
- SES契約の途中
- 客先常駐しているプロジェクトの途中
であっても、損害賠償の請求はされずに転職できるので大丈夫です。
客先常駐(SES)でプロジェクト途中で退職する場合の伝え方やメール文など、以下の記事で詳しく解説しています。
客先常駐・SESでプロジェクト途中で退職する場合の伝え方やメール文の詳細記事はこちら

やっておくべきこと番外編:引っ越しをする必要がある場合

社宅に住んでいる方や、次の職場の場所が大きく変わる方の場合、退職に合わせて引っ越しする必要があります。
賃貸物件は、DOOR賃貸で簡単に探すことができるので、活用してみて下さい。
DOOR賃貸は、キャリアインデックスが提供している賃貸マンション、賃貸アパートに特化した検索サイト。
特徴は以下の2つです。
- 大手検索サイトの物件をまとめて検索可能
- 入居が決まるとお祝い金がもらえる
素晴らしいのは、大手サイトの物件をまとめて検索可能なこと。
スーモ、マイナビ、アパマンショップ、エイブル、レオパレス21、centry21、ハウスコムなどの情報が一挙に見れるので、検索も楽チン!
また、全国500万件の賃貸物件があり、入居が決まると最大9.9万円のお祝い金がもらえます。
賃貸物件の空き状況は刻一刻と変わるため、引っ越しした方が良い方は、早めに登録しておきましょう。
TRY NOW
※最初から最後まで無料で利用できます!
退職までの期間が辛くて限界の方が取るべき方法

ここまで、
- 退職までの期間が辛くて気まずい時の乗り越え方
- 退職時にやっておくべきこと
について紹介してきました。
ただ、
「どうしても退職までの期間が辛すぎて耐えられない。。」
と限界の方は、退職代行を利用しましょう。
退職代行とはその名の通り、退職したい人の代わりに業者が会社とやり取りを代行してくれて、退職までをやってくれるサービス。
「会社に行くのが怖くなってしまった。。」
というぐらい、精神的苦痛を感じている方であれば、ストレスで大変なことになる前に退職代行を使って辞めた方がよいです。
すぐにでも逃げるべきヤバい会社の特徴と逃げの転職を成功させる方法の詳細記事はこちら

仕事から逃げたい20代・新人が逃げる時に転職で失敗しない方法の詳細記事はこちら

仕事から逃げたい30代が取るべき選択についての詳細記事はこちら

仕事から逃げたい40代が取るべき選択についての詳細記事はこちら

また、SES(客先常駐)で退職を言い出せなかったり、バックレてでも辞めたい場合も退職代行を使うのがおすすめ。
おすすめの退職代行サービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
SES(客先常駐)を辞める時におすすめの退職代行の詳細記事はこちら

なお、退職代行もいろんな種類があり、弁護士法に違反している退職代行も存在します。
当然、弁護士法に違反している退職代行を使うとヤバいです。
そのため、安心して使える退職代行サービスをつかうべき。
おすすめは以下の2つです。
- 利用者数NO.1で価格もリーズナブルな退職代行SARABA
- 弁護士による安心の退職代行サービス弁護士法人みやび
退職代行SARABAは、退職代行サービスの中で総合力トップのサービス内容と利用者数NO.1を誇ります。
退職代行SARABAの特長は以下の通り。
- 労働組合が対応するため交渉が可能(弁護士法違反の心配なし)
- 即日退職可能
- 利用料金は一律税込24,000円(追加料金なし)
- 万が一退職できなかった場合、全額返金保証付
- 行政書士監修の退職届付き
- 電話、LINE、メールに24時間即対応
- 無料の転職サポート付き
以下のような人にはおすすめです。
- 転職先が決まっているのに辞めさせてくれない
- 退職を伝えたのに受け入れてもらえなかった
- 上司や社長が怖すぎて言い出せない
- 仕事のストレスで精神的にしんどすぎる
- パワハラを受けている
- ブラック企業で体力的に限界
退職代行SARABAを使うと、バックレを考えるほどのクソな会社に人生を邪魔されることなく、次のステップに進めます。
合法的に強引に辞められるので、どうしても退職までの期間が辛すぎて耐えられない人は、迷わず使いましょう。
TRY NOW
※相談は無料でできます!
詳しくは以下の記事で紹介しています。

弁護士法人みやびは、労働問題に強く、弁護士でないとできないような業務である
- 有給休暇取得
- 残業代請求
- 退職金請求
- 未払い金請求
を行ってくれて、価格も破格な退職代行サービス。
弁護士法人みやびの特長は以下の通り。
- 弁護士でないと交渉すらできない業務を行える
- 他社の代行サービスで断られた困難なケースでも対応可能
- 退職希望者の権利を交渉・請求してくれる
- 即日退職可能
- 出社無しで引き継ぎ&私物引き取りもOK
- 全国どこでも対応可能
- 相談は無料で行える
- 着手金は弁護士依頼では破格の税込55,000円
- LINE、メールで24時間対応
以下のような人にはおすすめです。
- 転職先が決まっているのに辞めさせてくれない
- 退職を伝えたのに受け入れてもらえなかった
- 上司や社長が怖すぎて言い出せない
- 仕事のストレスで精神的にしんどすぎる
- パワハラを受けている
- ブラック企業で体力的に限界
- 有給休暇を取得して辞めたい
- 未払い残業代を請求したい
- 退職金の支払いを請求したい
- 未払いの給料を請求したい
転職先が決まったけど仕事を辞めさせてくれないとお悩みの方だけでなく、現在どうしようもないぐらいのブラック企業にいる方にもおすすめ。
どうしても退職までの期間が辛すぎて耐えられない人は、迷わず使いましょう。
TRY NOW
※相談は無料でできます!
詳しくは以下の記事で紹介しています。

退職までの期間が辛くて気まずい時の乗り越え方まとめ
お話してきたことをまとめます。
「退職までの期間が辛くて気まずい。。」と悩んでいる方が、退職までの期間を乗り越えるための心構えは、以下の2つ。
- 割り切る
- 次の職場への準備期間と考える
退職までにやっておくべきことは、以下の2つになります。
- 書類関連
- 引継ぎ関連
特に書類関係では、忘れがちな確定拠出年金やiDeCo(イデコ)の手続きも行っておきましょう。
退職までの期間が辛いし気まずい。。とお悩みの方にとって、参考になったら嬉しいです。
どうも、ポチのすけ(@pochinosuke1)でした~
仕事辞めたら人生楽しすぎ!ハッピーな毎日を送るためにやるべき方法の詳細記事はこちら

仕事を辞めてもなんとかなる!辞めたあとの生活が不安な方でも安心できる理由の詳細記事はこちら